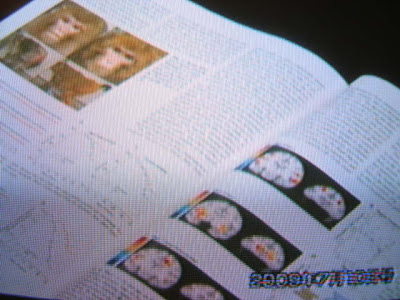2010年2月27日土曜日
心の動き = 気の流れ= 風水
これこれのアイテムをどこそこに置くと、運気がアップするなんていうのがありますが、おそらくこれはある程度は理にかなったことだと思います。
風水は東西南北の方角と部屋の位置などをどのようにしたらいいかといったことを教えるものですが、
そういうことを知らなくても、例えば南側をすべて壁にして日の光が部屋の中に入らないようにして、
食卓のすぐ横にトイレを配するなど、誰でもやりたくないと思うような配置にすることを想像してみれば、
そんな家に住みたいと思わない、つまりそういうものが日常生活の足を引っ張ることになるだろうことがわかります。
したがって、伝統的にこうした方がいいといわれていることは、
一般に多くの人が、そうすると心地よくなる、としたものを体系化したものであって単なる迷信、世迷言ではないと思います。
しかし逆に風水でこうするのがいいと言われているからと、それに縛られてしまって、
そこにいる人たちの心の動きを見ないというのは甚だ間違ったことだと思います。
おそらく基本は風水で伝統的にいいといわれるものを参考にしながらも、
自分、あるいはそこにいる人たちがどう感じているのか、どうすると気持ちがよくなるのか、心の流れが良くなるのか、
こういったことに注意しながら、自分たちにあった風水的な配置を発見していくことが大切なのかなと思います。
これは夢判断にも通ずるものがあると思います。
例えば夢判断といえばフロイトですが、20世紀初頭のオーストリアの人たちと現代日本に住む私たちの状況は大きく異なります。
したがって、夢であるテーマがでてきたとしても、それはフロイトの時代の性の抑圧が強かった時代にはフロイト流の解釈で合っていたかもしれませんが、
それが現代日本に必ずしもあてはまるわけではありません。
それは個についても言えて、
犬が大好きな人と、小さいころに犬に噛まれたことのある人が夢で犬を見たときにそれぞれに意味することが違うのと同じです。
それは各個人で考えなければならないテーマです。
しかしそれとは別にユングのいうような人類に共通する”原型”〔アーキタイプ〕みたいなものもあると思います。
おそらく風水として体系化されたものは、大多数の人に通ずる原理を体系化したもの、つまりをある程度の普遍性もつものだと考えられます。
もう一点、風水はモノを外界にどう配置するかという点でより客観性があるように思いますが、
見る人との関係性が重要であるという点では夢と共通するように思います。
たとえば植物を部屋においてみると、雰囲” 気”がガラッと変わったりします。
それは植物の持っているエネルギーみたいなものも当然あるのでしょうが、植物が置いてあるその部屋を見る人の心が動くからだろうと思います。
見る人が、そこに植物があるのはいいなぁ~と感じるとき、” いい気”が流れているということになるのでしょうか。
つまり風水というのは、客観的なものではなく、関係の科学なのだと思います。そしてそれは普遍的な要素と、個人的な要素の両方があると思います。
犬が嫌いな人が、運気がアップするといわれたからと部屋に犬の写真を貼ってみたところで、運気は下がるでしょう。
あと例えばこういう色の服を着るといいというのもありますが、
前に脳トレのところで触れたように、脳トレを始めた年配の人たちは、それまで地味だった服の色がカラフルになってくるというのがあるように、
おそらく心が浮き立ったときに好まれる色・形というのがあって、
それは逆にそのような外見にすることで、そこにいる人の心を高揚させるという働きがあると思われます。
こうすると心地いい、気持ちが良くなるという感覚を体系化したのが風水だと思います。
したがって、こうしたら運気がアップするといわれるものは当然参考にしたらいいと思いますが、それらを頭から信じこんでしまうのではなく、
基本は自分がどう感じるかを軸において、色々自分にとって心地いいカタチを模索していくこと、自ら確かめていくこと、
これが大事なポイントなのかなと思います。
では気とは一体なんなのでしょう。
私は気には狭義の気と広義の気があると思います。
狭義の気とは、精神(心)と物質(体)の中間的なエネルギーで、物質ほど確かさはないものの、心よりは実感できるものです。
仏教では、身口意の三業(しんくいのさんごう)という言い方があり、顕教(小乗・大乗)においては、体と言葉と心の働きをさしますが、
密教やゾクチェンのレベルになると、口(く)のレベルとは、単なる言葉ではなく、
精神と物質の間のエネルギーを意味し、それは言葉を発する時に空気が必要なように、身体のレベルでは呼吸と関わり、
心のレベルでは感情と密接に関連しているとされます。感情が動くとき、呼吸が激しくなるのは誰でもが経験することで、そのときに気が働らいていると考えられます。
日本語の"気が立っている"なんていう表現はまさにこれに当たるかと思います。
チベット語ではルン(風)といいますが、これはほぼ東洋における気と同じと考えていいと思います。
気は、心の側面から言えば、より物質に働きかけのある”念”というレベルと関連があり、
物質的な側面から言えば、素粒子のレベル、あるいは電磁波と関係しているのではないかと思います。
エレクトロンのことを電子、電子の動きを電” 気”というのは興味深いところです。
以上をまとめると、
◎物質(身体)
↑↓
〔素粒子・電気・呼吸〕
↑↓
◎気(口、ルン)
↑↓
〔感情・念〕
↑↓
◎精神(意・心)
となっているのではないかと思います。
では広義の気は何かといえば、森羅万象すべてということになります。
つまりあらゆる現象は一如であり、気の精粗によってすべてのものが成り立っているとする考えです。
気の粗いものが物質であり、気の細やかなレベルが心と考えるものです。
日本語で気といった場合は、
どうも心のレベルから狭義の気、すなわち口(く)、ルンのレベルを含んだものをおおざっぱに気と呼んで使っているように思います。
いずれにしても、
気の流れ= 心の動き
と密接に関連しているので、風水的な配置によって運気をアップさせたいと思うなら、伝統的に言われていることを参考にしながらも、
自分で確かめること、自らの感覚を研ぎ澄まし、自らの心の動きに敏感であること、これが大切なポイントなのであって、
人から言われたこと、本に書いてあることを単純にそのまま自分にあてはめてもどうなのかなと思います。
逆に、風水などは一切信じないという人も、
なんかイマイチ調子が出ないというときに、伝統的に風水で良いとされているものを一度試してみるというのもアリかなと思います。
おしまい
2010年2月26日金曜日
本領を発揮するために、、
注目の女子フィギアは、キム・ヨナ選手の金、浅田真央選手の銀に終わりました。
私はどちらが金を取るかということよりかは、
人はどのようにしたら自分の持っている力を遺憾なく発揮できるかということに興味があったので、
浅田選手にしても、キム・ヨナ選手にしても、それぞれが最高の演技ができたら素晴らしいなぁと思っていました。
演技を見ていて、キム選手の方は、最初から最後まで伸び伸びと楽しそうに滑っていたように思えましたが、
やはり浅田選手の方は、あの重たい音楽のせいもあるのでしょうか、
踊りに悲壮感がつきまとっている印象を受け、それが小さなミスを誘ったのかなという感が否めませんでした。
フリーは、順番がキム・ヨナ選手の次に浅田選手となっていたので、浅田選手がどのようにして待機するだろうかと興味をもって見ていたのですが、
イヤホンで自分の好きな音楽を最後までちゃんと聞いていたので、その点はさすがだなと思いました。
こういう小さなことをルーティーン化して、自分の最高の力を発揮できるようにもっていくというのは大切だなと感じます。
イチローなんかを見ていると、
彼は試合の始まる何時間前かに球場入りして、試合に臨むまでにどのようなメニューをこなしていくか、完璧に決まっているそうで、
あとはそれに従って自らの心と体を徐々に高めていくだけなのだそうです。
こういう自らを高める方法を体系化、ルーティーン化することで初めて、その人の本領が発揮されるのだと思います。
そしてこれは運動選手に限らず、私たちも活用すべきことだと思います。
たとえば受験にしても、このような細々とした原則があります。
ある定期試験の時、テストを返しながら先生がコメントを述べていました。
「皆さんはこれまでにずっと定期試験を受け続けてきて試験のエキスパートのハズなのに、
どうして今回は難しい問題のところで時間を食ってしまったんでしょうね。こういう問題は後に回して、解ける問題からやればよかったのに、、、。
と。
私はそのとき、ハタと思ったのです。
今まで試験のための勉強はしてきたが、
勉強法のための勉強、あるいは試験に臨むにあたっての細かなスキルに注意を払ってこなかったと気づいたのです。
そのときはそれ以上考えることはしませんでしたが、後々になってこの勉強法、試験の技術に注意するようになり、自分にあった勉強法として体系化しました。
たとえば、私には試験に臨む三大原則というのがあります。
1、難しい問題は後に回し、出来る問題からどんどん解いていく
2、ケアレスミスをしない方法を確立しておく
3、人と比較しない
試験というのは与えられた時間内に、相手のルールにのっとって、いかに得点を挙げるかというゲームとして捉えることができるので、
1の難しい問題を後回しにする、というのは当たり前のことなのです。
しかしこのことを試験に際して意識しているかしていないかで、
同じ実力があったとしても結果として大きな差が出てしまうのです。これはもったいないことです。
また2のケアレスミスに関しては、わかっていたのに問題の意味を取り違えたために得点につながらなかったということは誰にでも起こりうることです。
したがって、ケアレスミスをしない自分なりのスキルを確立し、習慣化しておくことも大きな差となって現れます。
私はたとえばセンター試験などでよくある、
「~にあてははまらないものを選べ」
つまり×のものを選ぶ時は、毎回ひと手間かけて問題文に×印を書いたりしていました。
また国語などの問題文にも、何が問われているのかをはっきりさせるために、問題文の問われている個所にぐりぐりと丸印をつけて強調させたりしたものです。
こういうひと手間は、一見時間のロスのように思えますが、ケアレスミスを防げるのでとても大きな差となって現れます。
あとは文章を読む前に設問を読んでおいて、
文章にはおおよそどのようなことが書かれているのか、また何に注意して読むべきかなどをピックアップしておいたりしたものです。
また最後の3.人と比較しないですが、
これは試験当日のことというよりは、試験当日までに、偏差値や倍率などの数値に振り回されないということです。
目標を人との比較に置くのではなく、
たとえば自分の受ける学校ではだいたい何割ぐらいを取れれば合格するというのがあるものなので、その目標ラインを自分が超えることに意識を注ぐのです。
これは荒川静香選手が、目隠しをして前の競技者の出来、不出来をシャットアウトしたというのに通じるかもしれません。
こうすることで、人がどうあろうが関係なく、自分が最高のパフォーマンスを発揮することだけに集中できます。
あとついでながら試験に関連して、私が体系化したことの一端を述べると、
試験の合間に、私は毎回自分の好きな梅ガムをクッチャクッチャ噛みながら、トイレに行きつつ、少しあたりをぶらついたりしていました。
ハタから見たらあまりお行儀よいものではないかもしれませんが、これも戦略の一つでした。
まず80分とか90分脳をフル回転させていると、ものすごくエネルギーを消費して疲労してくるので、
すぐエネルギーになる糖分を補給するとともに、顎を動かし、歩くことで脳、そして全身の血流を促して疲労回復につなげ、
外の新鮮な空気を吸うことで心身をリフレッシュさせ、
またそのついでに用を足しておくことで、試験中にトイレに煩わされないようにしました。
こういう細々としたことを私は限りなく収集し、自分なりに体系化して試験に臨みました。
こういうことをしておくと、失敗する確率が格段に減って、本番で自分の実力をほぼ100%発揮できるように思います。
ここら辺のことを「彦兵衛の勉強法」とでもしてどこかに書きたいなぁと常々思っているのですが、なんとなく書かずじまいになっています。。。
このように自分の本領を発揮できるようにまわりの環境を整えていくというのは、どこか風水とも関連しているように思います。
風水では運気を上げるということをいいますが、"気の運び"というのは、心の動きでもあり、そこにいる人の主観と関係しています。
ここら辺のことを次回、
心の動き= 気の流れ= 風水
として書いてみようかなと思っています。
つづく、、、
2010年2月23日火曜日
浅田真央とキム・ヨナ ~淀みと流れ~
明日からいよいよ注目の女子フィギアが始まります。
それに合わせて、数日前にNHKスペシャルで、
浅田真央 金メダルへの闘い
http://www.nhk.or.jp/special/onair/100221.html
という番組を放送していました。
その中で、浅田真央選手とキム・ヨナ選手が取り上げられていたのですが、
ふたりのあまりの対照的なあり方に唖然としてしまいました。
浅田真央選手の方には、コーチとしてこれまでにメダリストを十何人も育ててきたロシア人コーチ
がついているそうです。
彼女が指導をしている場面が写されていましたが、
見ていて踊っている様子があまり楽しそうではありませんでした。
エネルギーが流れていないというか、心が動いていないので体も縮こまり、演技が淀んで見えました。
なぜコーチがこのような指導をするかというと、浅田真央選手自身が、暗くて重厚感のある曲を選んだためです。
その曲は、
帝政ロシア末期の抑圧された民衆の心の叫びをテーマにした"前奏曲 鐘"というものです。
聞いていてとても重苦しく、外国人記者からも次のように質問されていました。
これに対して浅田選手は、
音楽を選ぶ時点で華やかなのと重厚な曲のふたつがあったが、
この曲を聞いたときに、力強い滑りが出来る気がしたのでこちらにした、と語っていました。
一方のキム・ヨナ選手がチョイスした曲はというと、
誰でもが知っている007のテーマ曲です。
キム・ヨナ選手自身、この曲に乗って滑れば滑るほど好きになると語っていました。
彼女をコーチしているのは、カナダ人で、
彼の戦略は、他の多くの選手がクラッシックを踊っている中、
皆が知っていて心弾むような音楽を流すことで観客を沸かせ、審査員に印象づけるのだと語っていました。
私はこの二人のあまりに対照的な選曲に、競技をする前から相当の差が開いてしまっているな、と感じました。
誰でも、軽快でノリのいい曲を聞くと、体が自然に動き出すという経験をしたことがあると思いますが、
ダンスによる表現力や、回転などの高い技術力が求められる場面で、
どちらの曲が有利かは言うまでもないことです。
しかも皆が知っていて共感できる曲というのは、観客もノッてくるので観衆からの力をもらえるのに対して、
浅田選手が選んだような曲だったら、ほとんどの人は知らないし、心がふさぎこんでくるので、
まず観客から力がもらえるということは期待できないように思います。
また審査の芸術点などは、もちろんパフォーマンスを見て決めるのでしょうが、主観の部分が大きく、
ノリノリの曲で鼓舞された方が、やはり点をつけたくなるものなのではないでしょうか。
そういう意味で、浅田選手の戦いはそうとう厳しいものになると私は感じました。
上にあげたポイントをまとめると、、、
浅田真央選手:曲が暗い、自分の体が重くなる、観客もノってこない、評価する側を鼓舞できない
キム・ヨナ選手:曲が明るく軽快かつ誰でも知っている、自然に体が動いてくる、観客もノってきて力をもらえる、評価する側を鼓舞できる
細々とした技などの前に、もっと土台となるこのような基本的な事柄はしっかり押さえておくべきなのではないか、、
とこういう競技を見るにつけ思うのです。
たとえば、前回のオリンピックで金メダルをとった荒川静香選手は、自分の競技前にはずっとアイマスクをして、自分の好きな音楽をヘッドホンで聞いて、
前の選手がどのような結果を出したかなど気にしないようにしていたといいます。
こういうことがいい結果につながるとわかっているなら、当然オリンピック代表選手の中で次の世代にも生かされているのかと思いきや、
フィギア男子の小田選手のコメントに、前の選手のパフォーマンスの最中に聞こえた観衆の声援に足がすくんだ、と言ってたのを聞くと、
荒川選手が実行して良かったことがオリンピック選手の中に受け継がれていないということになのでしょうか。
こういう心理的なものってものすごく大きいはずなのに、どうして生かされないのでしょうか。
あとたとえば、野球の日本代表と、サッカーの日本代表が比べられることがよくあります。
サッカーの代表がいつも大事な所で力を発揮できないのは、そのユニフォームの色に一因があるのではないかと私は思ってきました。
野球の日本代表のユニフォームは、理知と落ち着きをあらわす紺に情熱や闘志をあらわす赤のラインが入っています。
それに対して、サッカー日本代表は、ほとんど青一色です。
青は冷静さを保つにはいい色ですが、逆に闘志をかき立てるような色ではなく、ココ一番というところで心が萎えてしまう可能性があります。
逆にサッカーの韓国代表は常に赤ですが、野球の代表の方は西部ライオンズのようなブルーなんですよね。これは面白いです。
曲を味方につける、眼隠し・耳をふさいで、相手のことを気にしないで自分の最高のパフォーマンスに心がける、ユニフォームの色を改善してみる、
など些細なことでしょうが、人間は心が基本となって体が動くので、
心をどうやって鼓舞し、集中力を維持するかという細かなスキルはちゃんと競技前に準備しとくべきで、
それらを完璧にしたうえで技術を磨いていかないと、そういった土台、基本の部分が高度な技術の足を引っ張ってしまうことになるように思うのです。
スポーツ心理学ってちゃんとあるはずなんですけど、あまり普及していないのでしょうか。
こういうところにしっかりと焦点を当てて体系化し、トレーニングを積んでいる国は、そうとう強いと思います。
日本のオリンピック代表も、こうした知識を蓄積、体系化して、選手全体にいきわたらせるべきだと思うのです。大学でいう一般教養科目です。
そしてそのような知識は、競技者だけでなく、実は私たちにもあてはめることのできる、日常生活にも応用できるスキルだと思うのです。
国の代表として選手を送っているわけだから、単に勝ち負けだけでなく、
勝負に臨む上でどのような心がけが大切なのか、どのようなことが役に立つかを、出来たらこちら側に還元してほしいと思うのです。
さて今回のNHKスペシャルは、
浅田真央 金メダルへの闘い
という題でしたが、どういう結果になるのでしょうか、、、
音楽、パフォーマンス、観客の湧き立ち具合も含め注目したいところです。
おしまい
参考:
NHKスペシャル:浅田真央 金メダルへの闘い
http://www.nhk.or.jp/special/onair/100221.html
2010年2月22日月曜日
脳にいい食事、解毒作用のある食品
2010年2月21日日曜日
ホットケーキをメリケン粉から作ってみて分かったこと
最近朝食は、ウチで取れるミカンを1,2個あるいは、朝食を抜くというのが定番になってましたが、
なんとなく日曜日ということもあってラジオの音楽の泉でも聞きながらホットケーキを焼いてみたくなりました。
しかしホットケーキミックスがないので、家にあるメリケン粉(薄力粉)でホットケーキできないものか、、
とネットで情報を検索してみると、出来るんですね。
当たり前というか、パン系なのだから小麦粉から出来て当然ですよね。
しかし私の頭の中には、
ホットケーキ = ホットケーキミックスから作る
という黄金の方程式が成立していて、ホットケーキミックスがないとホットケーキが焼けないと思い込んでたところがありました。
どのHPでも分量はおおよそ、
薄力粉 100g
砂糖 30g
牛乳 1/2カップ
卵 1個
ベーキングパウダー 小さじ1と1/2
塩 少々
といった感じでした。
家に牛乳はないので、これは水で代用しました。
この分量で混ぜて、キジをちょっとなめてみるとあま~~い。
砂糖30gといったら、大匙で2、3回ドバッといれた感じです。(今回はきび糖というブラウンシュガーを使いました)
そうか、ホットケーキミックスもかなり甘いですが、あれにはこれと同じかそれ以上の砂糖が入っていたんだなぁと、驚きの発見でした。
焼いてみると、結構ホットケーキらしくうまく焼けました。
なんだ、ミックスなんてわざわざ買わなくても、ホットケーキ焼けるのね、と実感。
ただ牛乳の代わりに水で作ったので、コクがなくあっさりしたものになりましたが。。。
しかし焼きあがったホットケーキは、キジのときはあんなに甘く感じたのに、甘さをまったくといってもいいほど感じませんでした。
ということは、市販の菓子パンなんかの甘く感じるほどの砂糖の量といったら、凄まじい量になるんだろうなと想像します。
恐るべし、市販品であります。
考えてみると、缶コーヒーや清涼飲料水などでも、あの冷たさであの甘さを出すには、信じられないほどの砂糖を必要とします。
自分で水に砂糖を溶かして実験してみると実感出来るのですが、
こうして市販のジュースなどにどの位の砂糖が入っているかがわかると、あまりああいう類のものは飲めなくなります。
自分でやってみると色々なことが分かってきます。
そして既製品の恐ろしさがよく見えてきます。
中国餃子事件に限らず、あまり出来合いのものは食べない方がいいというのがよくわかります。
さてこの食品関連で、本日、面白い本を借りてきました↓

これはコンビニに立ち寄った時に書架に置いてあったもので、私はその題名に引かれてパラパラと読んでみました。
内容が今までこのブログに書いてきたこととも通じるようだったので、本日図書館で借りてきたという訳です。
さっそく興味のある章から読み進めたのですが、とても読みやすくどんどん読めてしまいます。
どのようなものが脳=体にいいのか、何が脳によくないのか、
鉛や水銀、カドミウム、アルミなどの体内の濃度と、子供の学習能力、IQ、多動性などの統計的な優位性が証明されているなど、興味深い報告が色々ありました。
これほどハッキリ結果が出てるというのは凄いなぁと思うとともに、日本は欧米ほどこれらの危険性が認識されていないというのもまた驚きであります。
またこの本は、単にそれらの危険性を指摘するだけでなく、
それらを取り除くためにどのようなものを食べたらいいのか、何を食べると解毒できるかなども書いてあり、とても参考になります。
基本的には、添加物が入っているものや出来合いのものを食べない(食肉や養殖魚を含む)、野菜や果物を多く食べる、ということのようです。
野菜や果物にはこういった金属類を輩出する働きがあるそうです。
この本は子をもつ親や、あまり体調がすぐれないひと、年配の方などは一度読んでみる価値があるのではないかと思います。
以下に目次を載せておきますので、興味のある方はざっとでも見てみてください。
エドガー・ケイシーは、「人は食と思考によってつくられる」と述べていますが、最近よくこのことを実感します。
食・運動・睡眠、そして想念の習慣は、毎日のことだけにホント注意していきたいな、と思います。






おしまい
参考:
生田 哲 著 (2008/10/16)
食べ物を変えれば脳が変わる (PHP新書)
アマゾン内容紹介
脳と心を最適な状態にするために、今すぐ始められる食習慣とは何か。例えば青魚を食べること、コーヒーを控え目にすることだ。
サンマ、サバなどからDHAを摂取すれば、頭の回転が速くなる。水分を除けば、脳の四分の一はDHAなのだ。妊娠期、授乳期の女性には特に重要である。さらにDHAは、うつの改善やアルツハイマー病予防にも効果があるのだからすごい。
一方コーヒー依存になると、「アデノシン受容体」が増えてカフェインへの耐性が強まり、少量のカフェインでは興奮できなくなる。するとさらに大量のコーヒーを飲むことになり、やがて脳や副腎が疲弊してゆく。
その他本書では、集中力や記憶力を高める食べ物や、脳をダメにする物質(鉛や水銀など)とその解毒法など、薬学者が脳と心にいい食事、悪い食事について、治験による裏付けを明記しつつ平易に解説する。読んで本当によかったと思える一冊。
内容(「BOOK」データベースより)
脳と心を最適な状態にするために、今すぐ始められる食習慣とは何か。例えば青魚を食べること、コーヒーや白砂糖を控え目にすることだ。サンマ、サバなどからDHAを摂取すれば、頭の回転が速くなり、さらにうつの改善やアルツハイマー病の予防にも有効。妊娠期、授乳期の女性には特に重要である。
一方コーヒー依存になると、脳や副腎が疲弊してしまう。白砂糖をとりすぎると血糖値を乱して精神を不安定にする。本書は脳と心にいい食事、悪い食事について、治験による裏付けを明記しつつ平易に解説する。
生田 哲
1955年北海道函館市生まれ。東京薬科大学卒業。がん、糖尿病、遺伝子研究で有名なシティオブホープ研究所、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)などの博士研究員を経てイリノイ工科大学助教授(化学科)。
薬学博士。アメリカで遺伝子の構造やドラッグデザインをテーマに研究生活を送る。現在は日本で、精神や心のはたらきを物質レベルで解析し、生化学、医学、薬学などライフサイエンスを中心とする執筆活動を行なっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
2010年2月20日土曜日
赤ヒヤシンスが咲いた
赤ヒヤシンスが本日満開となりました。
2/15〔月〕から咲き始めました。
毎日写真に撮ってみたので並べてみます。

2/15朝

2/16朝

2/17朝

2/17夜

2/18朝

2/18夜

2/19朝

2/19夜

2/20朝
今朝が満開でした。
花は咲いたのですが、背丈は青ほど大きくなりませんでした。

種類が違うのでしょうね。
青の方はというと、、

一本が、くたーーっ、と曲がってしまいました。。。
さいごにおまけ↓

これは豆苗(とうみょう)という生で食べる野菜です(80円くらい、結構オイシイ)。
新品ではなく、一度全部上を切って食べたあと、適度に水をやりながらおいときました。
二週間ぐらいでこのように新品と同じような感じに生えてきました。
何回いけるんでしょうかね。これだけ生えてくるなら、一回で捨ててしまうのはもったいないですね。
植物が成長していく様子を見ているのは面白いものです。
おしまい
2010年2月16日火曜日
若さを保つ鍵とは、、~サーチュインの活性化~ 2
誰の体内にもあるサーチュイン、これを活性化させるにはどうしたらいいのでしょうか。
そのヒントは70年前の研究にすでにあったそうです。
それはマウスの栄養と寿命に関する論文でした。
この研究によると、カロリーを制限すると、マウスの寿命が延びることが分かったのだそうです。
それと同じことが人間にも見られました。
第二次世界大戦中、ストレスによって心臓病で早死にする人が増えると誰もが予想していたそうです。
しかし実際のところ、心臓病で死ぬ人は2割減ったのだそうです。(このことはエコロジカル・ダイエットでも紹介されていました。)
研究者たちは、戦時下のカロリー制限によって、
心臓病になる人が減ったのだと考えましたが、科学的な証拠はありませんでした。
しかし近年、それを裏付けるような研究結果がでたそうです。場所はアメリカ、ウィスコンシン大学。
ここでは、76頭のアカゲザルを20年にわたって飼育し、カロリーの違いが個体にどのような影響をもたらすかを研究してきました。
こうして育てられたカロリー制限をしなかった個体は外見はこんな感じ↓
カロリーを30パーセント減らして育てた個体はこんな感じ↓
同年齢の2匹を並べて比べ見ると、その違いは一目瞭然です。
この20年間の研究成果が、去年2009年、サイエンスに発表されました。
それによると、カロリー制限なしで育てた方はすでに半数が死んでしまったにもかかわらず、
カロリー制限をしていた個体は8割がまだ生きているのだそうです。
ではカロリー制限をすることで、なぜ長寿がもたらされたのでしょう。
マサチューセッツ工科大学のレオナルド・ガレンテ博士は、カロリー制限をしたネズミの組織の中のサーチュインタンパクの量を計測したところ、
各臓器の中で、カロリー制限をしていた方はサーチュインタンパクが多かったのです。
つまり、カロリー制限をすることはサーチュインの活性化につながり、それが、ガンや糖尿病、動脈硬化などを防ぎ、長寿をもたらしたと考えられるのだそうです。
これは生体が栄養の少ない過酷な環境をなんとしても生きぬき、子孫を残そうとする働き、
つまり生物の生き残り戦略としてこのような機能が生体に備わっているのではないかと推測されているそうです。
番組内では、他に赤ワインにもサーチュインを活性化させる効果があることが紹介されていましたが、
その効果を得るためには、赤ワイン100杯だったかの量を一度に摂取しなければならないとのことで、まったく健康からは程遠いということだそうです。
他に薬を飲んでサーチュインを活性化させるなどが検討させているそうですが、まだ研究段階だそうです。
昔からたとえば日本でいえば貝原益軒の『養生訓』などにも
食事は腹八分なんてことがいわれてきましたが、少食が体に良いことは昔から経験的に言われてきました。
しかし今回のように科学的な見地、分子的なレベルから裏付けられたというのは画期的なことだと思います。
現代の先進国においては、あまりに飽食が進み、それによって様々な病が発生しているわけですが、
その病の根本である食事を制限するのではなく、飽食のまま薬や手術で対処しようという本末転倒なことがなされています。
今回のような研究が、健康の本質である人間の正しい食のあり方を見直す上で大いに参考になるだろうと思います。
ただし食べるということは、単に「栄養をとる」ということ以上に、「楽しむこと」でもあるので、
何が何でも量を減らさなければというのもまた問題だとと思います。
毎食、毎食、好きなものを好きなだけ食べるというのではなく、ここで発表された結果を念頭に置きながら、
なるべく控え目に食べるように心がけるというだけで相当違ってくるだろうと思います。
また食事の内容も、カロリーの高い肉・乳製品などを減らして、野菜にシフトする、砂糖やお酒などを控え目に摂るというように心がけるだけでもだいぶ違うと思います。
今回ゲストとして招かれた札幌医科大学の堀尾嘉幸教授(サーチュインの研究者)によると、
サーチュインというのは生体の中で指揮者のような役割を果たしているといいます。
様々な器官、組織からなる体全体をオーケストラに譬えるなら、その全体を指揮、統括するのがサーチュインのようです。
そしてそのサーチュインは少食によって発動するというなら、この機能を活用しないなんて宝の持ち腐れのようなものです。
前に紹介したように、何代にもわたって極端なベジタリアンを続けてきたバラモン階級のひとたちのようになると、また逆に体に支障をきたすと思いますが、
現在の食事から、肉・乳製品を減らして野菜を多くするぐらいなら、まったく問題ないと思います。
その時大事なのは、野菜もなるべく全体を食べる、
たとえば米なら玄米、パンもなるべく全粒のもの、砂糖を使うなら、精製していないブラウンシュガーを使う、
大根などは葉っぱもたべるなど、などの気配りが必要だと思います。
こうやって正しいことが科学的にだんだん明らかになって来るというのは、嬉しい気がします。
栄養や運動・健康に関する知識は、新たな発見があって、どんどん新しくなっている側面もあるので、
このような知識には常に耳を傾けておきたいと思っています。
結局、日々の小さな積み重ねが、10年、20年後にあらわれてくるので、毎日行う基本的なことがらは大切にしていきたいと思っています。
おしまい
参考:
サイエンスゼロ:長寿遺伝子が見つかった!
http://www.nhk.or.jp/zero/contents/dsp290.html
日経サイエンス:特集:長寿の科学
「長生き遺伝子」の秘密を探る
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/0605/aging-sa.html
バラモンの菜食主義〔彦兵衛のブログ〕
http://mshiko.blogspot.com/2008/08/blog-post_22.html
アマゾン↓
養生訓―全現代語訳 (講談社学術文庫 (577))
葬られた「第二のマクガバン報告」(上巻)
エコロジカル・ダイエット―生きのびるための食事法