日本の首相に、初めて女性が就くことになりました。とても素晴らしいことで、応援したいと思っています。
就任早々の言葉で、「ワークライフバランスを捨てる」との発言をし、各方面から批判されることがありました。私も最初それを聞いたときは、
あーそれはダメだな、両方のバランスをとってこそ、どちらもうまくいくのになー、、
と思っていたのですが、少し経ってから思ったのは、
何かスイッチが入ったからあのような発言になったのではないか、、
ということでした。
たとえば、本田宗一郎さんは、車を作ることが好き過ぎて、夢中になってやってたら、いつのまにか深夜になっていた、、ということがあったそうですが、
それはもう楽しくて、まさに寝食を忘れて没頭してしまったということになるのだと思います。
それは端から見たら努力というように映るのかもしれませんが、本人は、楽しくて楽しくてたまらない、という感覚だったのだと思います。
それと同じように、高市さんも、何かそのような神がかったスイッチが入ったため、もう楽しくてしょうがなくて、あのような発言になったのではないか、、という気がしました。
いずれにしろ、頑張って頂けたらと思っています。
今回書こうと思ったのは、やはり高市首相に関してなのですが、就任して早々に外交の旅に出ました。
ニュースで、彼女が何か話している場面があって、あー、東南アジアの何か現地の言葉で話しているのかな、、と思っていたところ、よく耳を澄ますとそれは英語でした。。
え、高市さんってアメリカで議員さんのもとで働いていたこともあるんじゃなかったっけ、、それでこの発音、、。
ちょっとビックリしてしまいました。
私達、日本人が学んできた英語は、英語と言っても米語で、特にアメリカの東海岸の方の英語をスタンダードとして学んできています。
したがって、本家本元のイギリスの人が話す英語を聞くと、あれ、なんか違うな、、という気がするし、世界中には、英語を母国語としない国々のひとも英語を話していて、英語も色々なバリエーションがあっていいと思います。
私はインドに住んでいたこともあって、インド英語というのはよく聞いていましたが、チベット人の友人がインド人の英語をマネするのが凄くうまくて、いつも楽しませてもらっていました。
日本人の英語は日本語っぽいカタカナ英語になりがちですが、それはそれでいいと思います。
ただし、言語はあくまでも意思を伝えるツールです。そのツールを使って意味が伝わらなければ用をなしません。
私は高市氏の英語のスピーチをいくつか見てみましたが、部分、部分でどうしても何を言っているのか何度聞き直してもわからない箇所があり、それはどうもネイティヴの人たちが聞いても同様のようでした。
私は言語に関しては、発音がいい(流暢)というのを縦軸、意味が伝わるというのを横軸にして次の4つの領域に分類されると思います。
① 発音がよくて、意味が伝わる
② 発音が良いが、意味が伝わらない
③ 発音はよくないが、意味が伝わる
④ 発音が良くなく、意味も伝わらない
《発音》
↑
② | ①
-------+--------------→ 《伝わる》
④ | ③
|
今までの日本人の首相の英語というのは、だいたいにおいて③ではなかったかと思います。
私が英語の発音がいいな、しかもよく伝わる、、と思った首相は、最近で言うと、岸田首相ですね。
ゆっくりと明瞭に英語を話されていて、凄くいいな、、と感じていました。ちょっと話し方がダライ・ラマ氏ににいてる気がしていました。
上の表で言うと、③よりかは①に近い方だったような気がします。
一方、高市首相は、ときに不明瞭で本当に何をいっているのかわからない箇所があり、上の表で行くと、③と④の中間たありにあるのかと思います。
高市首相の英語に関する評価が賛否両論に別れるのも、この点にあるからではないかと思います。
完全に④(発音が悪く、意味もまったく伝わらない)なら、一斉にやめるような声が上がると思うのですが、
だいたいにおいて伝わっている部分と一部まったく伝わらない箇所がある点で意見が別れると思うのです。
私は、高市氏は当然、相当ネイティヴに近い感じで話されるのだろうな、、と思っていただけに、そのギャップがあまりにあったため、少し愕然としてしまいました。。
あるネイティヴの人は、高市さんの英語をそのまま外交の場で使うのは危険だということを述べていました。
発音が良くないだけならまだしも、何をいっているか意味が伝わらなければ確かに危ういと私も感じます。
一つの言葉の使い方や解釈で、外交問題となることは過去にもありました。
有名なのところでは、1972年のいわゆる「ご迷惑問題」です。 当時の首相田中角栄氏は、晩餐会の折、「中国国民に対して多大のご迷惑をかけた」と発言し、そのご迷惑という語を「添了麻煩」と訳したため座が凍りつき、周恩来氏が激怒したというものです。
「添了麻煩」という言葉は、ご面倒をおかけした、すいませんでした、といった軽い意味だったようで、双方の意味の解釈の違いによって生じた問題でした。
参考:ウィキペディア:添了麻煩
また言葉ひとつで外交問題になったというので記憶に新しいのは、ゼレンスキー大統領とトランプ大統領との会見です。バンス副大統領が
「(ウクライナの)平和と繁栄への道とは、外交に関与することだ。まさにトランプ氏が行っていることだ」
と発言したのに対し、ゼレンスキー大統領が「外交とはどういことですか?」と噛みついたことから始まりました。
ゼレンスキー大統領としては、外交が失敗しているからウクライナが侵攻されているんじゃないか、という思いがあったのでしょうが、
この副大統領の発言はもともとトランプ大統領をたたえる発言であり、ここで「外交とは何を意味するのか?」と発言するのは、おそらく前後の内容を理解できておらず、部分的な内容から感情に火がついてしまったのではないかと推測されます。
これも、母国語でない言語で話し合っていたために起こった問題と言えるのではないかと思います。
参考:ダイヤモンド・オンライン:そりゃトランプもブチギレるわ…通訳なしでしくじった「ゼレンスキー英会話」の不適切表現3選
外交の場では、このように言葉一つで、大きな問題に発展する可能性もあるので、私は、高市首相には、日本の立場を表明するような場で、英語でスピーチするのはあまり得策ではないと思います。国益に関わってくると思います。
むしろ、そのような場では、美しい日本語で堂々と話し、英語の方は、プロフェッショナルにまかせてしまえばいいと思います。
ただし、日本の立場を正確に伝えなければならないような公式な場ではなく、インフォーマルな場で、英語を話すことでポジティヴにとってもらえるような場所においては、積極的に英語でお話をされたらいいのではないかと私は思います。
日本初の女性首相には、たいへん期待しているので、ぜひ張り切って、頑張って頂けたらと思っています。
タイトル:不得意なことは人に任せてみては、、
でありました。
<(_ _)>
おまけ、、
ギャラリー:空の風景、、
最近、明け方の空がとても魅力的なので、
おっ!と思ったときにすかさず写真を取るようにしています↓







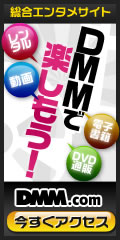

0 件のコメント:
コメントを投稿