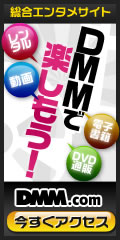-
最近よく、
伊勢ー白山 道さんのブログを読ませていただいてます。彼は霊的、神的なものを感じる能力がある方のようです。彼の説くところはたいへんシンプルでありますが、同時にとても本質をついていると感じます。(詳しくは伊勢白山道さんのブログまたは、著書『
内在神への道』を読んでみてください。)
伊勢白山道さん曰く、最強の祝詞とは、
生かして頂いて、ありがとうございますだそうです。また続けて
アマテラスオホミカミ・アマテラスオホミカミと唱えると良いそうです。
また、ご先祖の方々や神さまに対しては「お願い事」をするのではなく、ひたすら感謝をすることが大切だといっていますが、これと共通する「感謝することの大切さ」を説いた話を最近読んだ本の中に見つけました。
『神道見えないものの力』 葉室頼昭 春秋社 1999という本です。作者は春日大社の宮司の方ですが、もとはお医者さん(大阪大学医学部卒)という変わった経歴の持ち主で、不思議なことに御親族は(たとえ血がつながっていなくても)みななぜか最終的には宮司をしているという変わった家系のようです。
この本のなかでは、
生かされるいることに対する感謝の気持ちをもつことの大切さが説かれていて、なるほどなと思わされる点がたくさんありました。また「自殺」についてや「はたらく」ことの意味の解釈も面白かったのでついでに載せておきます。
------------------
バランスと真実の健康日本人は、罪・穢、つまり我欲によってバランスが崩れることを知っていたから、
常に我欲をなくして、神さまに生かされている生活を目指してきたのです。これは自分でバランスを整えようとしなくても、神さまはちゃんとバランスが整うように、人間の体をしてくださる。そういう考え方です。これが
生かされているという考え方です。
自分で生きているというと、自分でバランスを整えなければいけない。不可能ですよ。
百パーセントのバランスを自分の力で維持するなんていうことは、できるわけがない。歯を一ミリ削ってもバランスが崩れるわけですからね。
ですから、そんなことができるわけがないから、日本人は罪・穢を祓いましょう。我欲を亡くしましょう。すべて神さまに生かされる生活をしましょう。そうしたら神さまはバランスを整えてくださって、健康な生活をさせてくださる。そういって昔から真実の生活を送ってきたのです。これは最高の生き方だと思います。
ところが、外国人は、薬とか何かで、
自分の力で健康を作ろうとするでしょう。そこで間違ってきてしまうんです。ですから、私は日本人の、つまり神道の考え方というのはすごいと声を大にして言っているのです。世界にまれなる考え方ですから、これを実践している日本人が世界を救うというのは当たり前なんです。何でもないようですが、
しかしすべて我欲をなくす生き方というものが、これからの人間の生き方の目標にならなくてはならないでしょう。
<中略>
人間の体というのは疑いようもなくバランスで健康が保たれているのです。それは人間の力だけではほとんど不可能です。ですから、「
ありがとうございます」と神さまに感謝しなさい。そうしたら我欲が消えてバランスが整います。薬の何百倍も効くパワーが生み出され、病気を消し、バランスを整え、健康になるのです。
<中略>
ですから、
病気でも何でも不幸なことは、感謝というものの大切さを分からせるために与えられた神さまのお知らせだと思うんです。さっきも言ったように、夜を知らせるためにはまったく反対の昼を見せなければ、夜が分からないのと同じように、病気というのもを見せなければ、健康のありがたさというのは分からないんですね。
神様はすべて正反対のものを見せて、本当のものを知らせようということなんです。これが自然の仕組みです。神さまがいらっしゃるなら、なぜこんなに不幸があるのか、悩みがあるのかと言う人がいますが、そういうものがなければ、本当のありがたさというのは分からないんです。
<中略>
ですから、
病気になったら、感謝が足りないんだなと気が付けばいいんですが、それに気が付かずに、薬とか何かで治そうというから間違ってくるんです。本当に感謝するということが一番大切なことなのです。
(p.180-187)
本当に生きるとは― そういえば、お年寄りの方の自殺が非常に多いという話もききますね。
これも戦後の悪弊で、ひとつに
人間は自分で生きているという考えになってしまってから、こういう自殺というのも増えているんですね。生かされているということを忘れてしまったんでしょう。才能に恵まれた人が自殺をする例が非常に多い。
<中略>
戦後、老人の自殺が多いというのそれですね。自分のことだけ考える。世の中の幸せのために生きるとか、そういうものがなくなってしまった。そうすると、行き詰ってしまうんですね。人間というのはそうではなくて、いつも言うように、神を認め、神をたたえなければいけない。それは人間に対しても同様で、
人のいいところを認めてあげてほめるというのが、人の本来の生き方なんです。それなのに逆をやるようになってしまったから、しまいに人生に行き詰まりを感じるわけでしょう。
しかし、
神を認めるということに行き詰るということはない。永遠に行き詰まりというのはないわけです。だから、人生に行き詰まりというのはないわけです。自分のことを考えると行き詰りになってしまうんです。
― 自分のことだけ考えていると行き詰ってしまうと。
ええ。だからそうではなくて、人を喜ばせることを考えれば、行き詰りということはないでしょう。一生懸命に働くというのは、外国では労働だけれども、日本語は「
はた」を「
らく」にする。周りを楽しませるというのが働くということです。これはすごいことだと思うんです。自分のために働くから、行き詰ってしまうんです。そうではなくて、
人を喜ばせるためだったら、行き詰りというのはない。どれだけの人を喜ばせたら終わりというのではなくて、対象は無限でしょう。そうすると、自殺なんかしていられなくなるわけ(笑)。
(p.211-213)
--------引用終了----------



















.jpg)